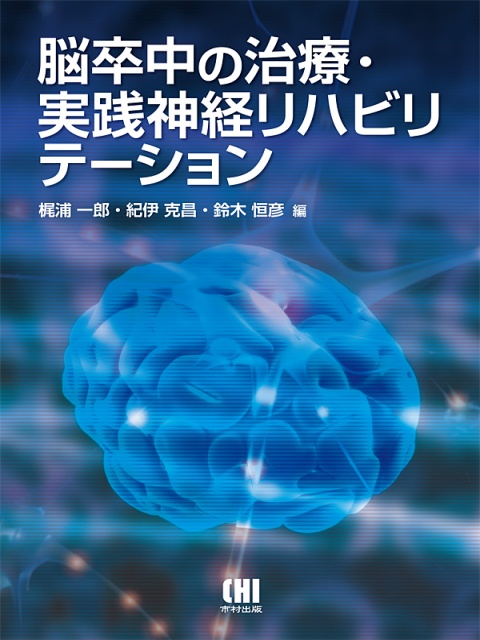脳卒中の治療・実践神経リハビリテーション
脳卒中の治療・実践神経リハビリテーション
(book0037)
編著者
梶浦 一郎/鈴木 恒彦/紀伊 克昌
書籍データ
【発行日】 2010年8月刊行
「脳卒中の治療・神経リハビリテーション」の出版に寄せて
国立循環器病センター名誉総長
(社)日本脳卒中協会理事長
山口 武典
脳卒中は死因こそ現在第3位ですが、寝たきりや、要介護の最も多い原因となっている疾患です。治療には総医療費の1割弱が費やされ、入院して治療を受けている患者はがん疾患の1.5倍、心臓病の3.5倍にも及び、国民病ともいうべき病気です。脳卒中を起こすと、患者はたとえ死に至らなくても運動障害、認知機能障害などの後遺症に苦しみ、家族には精神的にも経済的にも大きな負担が掛かって、家庭崩壊にも直結しうる大きな社会問題です。脳卒中の患者数は、現在280万人弱と推測され、人口の高齢化に伴って更に増加しつづけると予測されています。
欧米では、脳卒中のことを「ストローク(神の一撃)」と呼び、「人の力ではどうしようもない運命」とあきらめていました。それが、CTやMRIなどの診断技術の進歩、t-PAによる血栓溶解療法などの新しい治療法、あるいは脳卒中専門病棟「(ストローク・ユニット)の登場」あるいは発症早期からの積極的なリハビリテーションによって「治せる」病気に変貌し、「治る」イメージの強い「ブレイン・アタック」と呼ばれることが多くなりました。これらの新技術の中でも、神経科学の新たな知見に基づくリハビリテーションは、強力な戦力の1つです。本書がその普及の一助となることを願ってやみません。
なお、われわれは脳卒中診療における新技術を普及し、脳卒中対策を一層充実させるには、脳卒中対策の法制化、すなわち「脳卒中対策基本法」(仮称)の制定が必要と考え、既にその原案を提案して運動を展開しています。ぜひ皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。(http://www.jsa-web.org/law/hou9a.html)
序文
脳卒中後のリハビリテーション(以下リハビリ)は、我が国のリハビリの中では最も接する機会が多い身近な存在である。最近の傾向は、可能な限り発症から回復期に至る3ヵ月以内に、集中的にできれば1日3時間かけて神経リハビリを行うことが推奨され、効率的・効果的アウトカムをもたらす手法が求められている。しかし具体的には、どのような障害にどのようなリハビリをどの程度行うのが適切かは良く分っていない。また医療的リハビリだけで解決できないこの分野では、回復期以後の在宅や施設での生活リハビリに関わる福祉的リハビリサービスとの連携のあり方が常に問題になる。これらの課題に実践的に答えようと企画したのが本書である。
包括的に脳卒中のリハビリをまとめようとすれば、エビデンスに軸を置いた標準的評価・治療の原則論に終始した解説書となり、一人ひとり異なった問題を本来有する脳卒中患者の顔が見えなくなる。一方、個々の実践的な症例提示に徹した実例書の場合、どのような切り口でまとめるのか、収集がつかない恐れがある。本書では、セラピストが日々の脳卒中患者の障害像をあるコンセプトを持って、多面的切り口から分析し、最新の脳科学の知識を動員して考え、ハンドリングを行うボバースアプローチに着目した。その技術と知識において、国際ボバース講習会講師会議(IBITA)は、目下のところ世界で最も厳しい認定基準を有するからである。編者の一人である同国際シニアインストラクターである紀伊克昌氏にお願いし、IBITAの構成員である日本ボバース講習会講師会議(JBITA)の諸氏に、それぞれの得意分野を趣旨に沿って実践的にまとめていただいた。一般的に文献や出版物は、その時代毎の最新情報を提供できるものの、進歩する情報からは出版と同時に常に遅れてしまう宿命にあり、本書も例外ではない。日々変わる最新情報に遅れず、新たな技術を発展させるためには、脳卒中後遺症に対する自ら自信を持ったコンセプトをたえず維持する必要がある。したがって本書から汲み取っていただきたいのは、底流にある脳卒中後遺症に対する不変(=普遍)的コンセプトである。以前から脳卒中後遺症のリハビリは、訓練というより「最適応のための中枢神経系の学習」を主張してきたボバースアプローチは、現在常識的となっている神経可塑性の概念を背景にして、麻痺側・非麻痺側を考慮した運動学習を考えていたといえる。学習を考える場合、御本人の周りのリハビリ環境が重要であることの論は待たないが、実践場面では、どんな刺激入力がどの時点で有効なプログラムを再構築できるのかが判然としない。しかし有効に働いた時の患者の表情や姿勢・行動(動作)は喜びに溢れ、よく調整された筋緊張の状態を呈することは誰しも経験しているはずである。ただ意欲を持って再適応に臨める患者は現実には少ない。適切な刺激入力にもかかわらず、フィードバックで始まる学習は、患者にとっては先の読めない不安な一歩だからである。目標のある姿勢・運動では、構成筋群の緊張を強めずとも受け入れが可能であり、繰り返しによって自信を持つはずである。治療―評価を通した患者(その中枢神経系)との間のコミュニケーションの醍醐味をひとりでも多くの方々に経験できるようなお手伝いが本書を通してできればこれ以上の喜びはない。
2010.7.
編者 梶浦 一郎 ・ 鈴木 恒彦 ・ 紀伊 克昌
編者 梶浦 一郎 ・ 鈴木 恒彦 ・ 紀伊 克昌